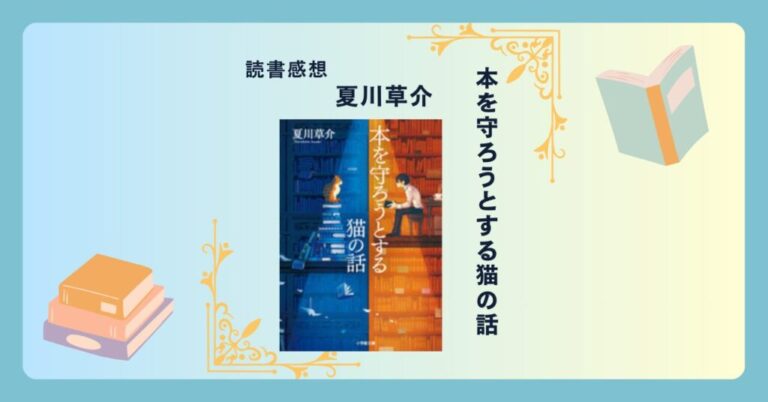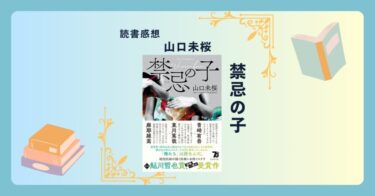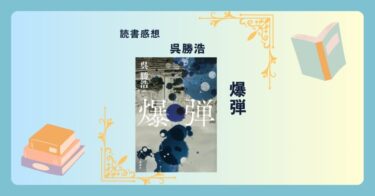読書感想です。今回は夏川草介さんの「本を守ろうとする猫の話」です。
米国、英国をはじめ、世界35カ国以上で翻訳出版されているロングセラー小説です。
記事前半はネタバレは含みません。「続きを読む」を押さない限りネタバレ内容は見えませんので未読の方も安心してお読みください。
作品情報
- 作品名:本を守ろうとする猫の話
- 作者 :夏川草介
- 出版社:小学館(小学館文庫)
- 頁数 :288P
こんな人におすすめ
- 本が好き
- 本をより好きになりたい
- 爽やかな物語が読みたい
特徴グラフ
※私個人の見方・感想です。
あらすじ
『「お前は、ただの物知りになりたいのか?」
夏木林太郎は、一介の高校生である。幼い頃に両親が離婚し、さらには母が若くして他界したため、小学校に上がる頃には祖父の家に引き取られた。以後はずっと祖父との二人暮らしだ。祖父は町の片隅で「夏木書店」という小さな古書店を営んでいる。その祖父が突然亡くなった。面識のなかった叔母に引き取られることになり本の整理をしていた林太郎は、書棚の奥で人間の言葉を話すトラネコと出会う。トラネコは、本を守るために林太郎の力を借りたいのだという。
お金の話はやめて、今日読んだ本の話をしよう--。』
引用元:小学館
感想
ファンタジー小説
主人公の高校生である夏木林太郎が、古書店でともに暮らしていた祖父の死をきっかけに孤独を抱える中、喋る猫とともに「本を守る」冒険を通じて成長していく、心温まるファンタジー小説です。
爽やか、軽快、読みやすい
章立てが明解でテンポよく読み進めることが出来ます。
内容や登場人物に嫌みが一切なく、友人とのちょっとした青春要素などもあり、爽やかな読み心地です。
本への向き合い方を考える
主人公は、本好きが抱えるジレンマに立ち向かっていきます。
例えば、ただたくさん本を読むことがえらいのか?素早くあらすじを追えればいいのか?など。本が持つ力やその価値は何なのかを主人公と共に考えていきます。
本好きにとって共感の嵐であると同時に、普段本に触れる機会が少ない人々にとっても、本の魅力を再発見するきっかけになると思います。
作中に多くの有名な作家名や作品名が登場します。またそのオマージュやパロディが織り込まれているとのことで、それを見つけてみたり、他の作家さんや作品に興味を持ったりという楽しみもあります。
以下、内容に触れた感想を記載しますので、開く際はその点ご了承ください。
感想(ネタバレ有り)
他の読者の感想
こちらをご覧ください。
※ネタバレ感想も含まれますので見る際はご注意ください。
まとめ
以上、夏川草介さんの「本を守ろうとする猫の話」の読書感想でした。
未読の方は是非手に取ってみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。