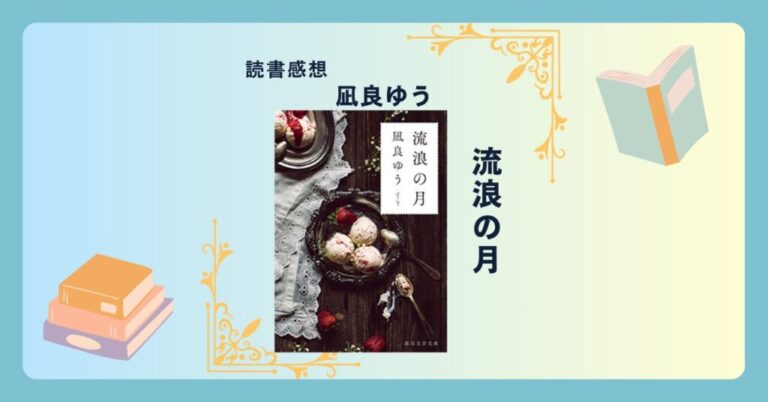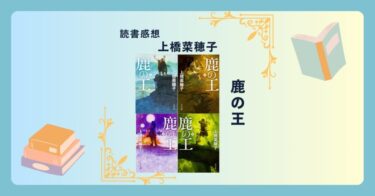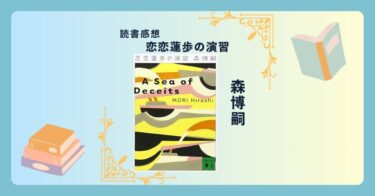読書感想です。今回は凪良ゆうさんの「流浪の月」です。
2020年本屋大賞受賞作品です。映画化もされている有名作品ですね。
記事前半はネタバレは含みません。「続きを読む」を押さない限りネタバレ内容は見えませんので未読の方も安心してお読みください。
作品情報
- 作品名:流浪の月
- 作者 :凪良ゆう
- 出版社:東京創元社(創元文芸文庫)
- 頁数 :356P
こんな人におすすめ
心の機微をじっくり味わいたい
世間の“普通”や“常識”に違和感を覚えたことがある
重たいテーマにも向き合える
特徴グラフ
※私個人の見方・感想です。
あらすじ
『最初にお父さんがいなくなって、次にお母さんもいなくなって、わたしの幸福な日々は終わりを告げた。すこしずつ心が死んでいくわたしに居場所をくれたのが文だった。それがどのような結末を迎えるかも知らないままに――。だから十五年の時を経て彼と再会を果たし、わたしは再び願った。この願いを、きっと誰もが認めないだろう。周囲のひとびとの善意を打ち捨て、あるいは大切なひとさえも傷付けることになるかもしれない。それでも文、わたしはあなたのそばにいたい――。』
引用元:東京創元社
感想
誘拐事件?
9歳の更紗は、ある日ひとりの大学生・文に誘われて、その家に居候することになります。
しかし、それは世間から見れば「誘拐事件」とされ、二人はそれぞれ加害者・被害者というレッテルを貼られることとなります。
世間の常識や“正しさ”の物差しでは測れない、人と人との関係を描いた作品です。
ページ数は文庫版で約300ページくらい。
章立ても多すぎず、スッと読める構成になってるので、あまり時間をかけずに読み進めることが出来ます。
文章はとても丁寧でやわらかく、文体も平易だから読みやすいです。
静かに激しく訴えかけられる
この物語は、とても静かで、けれど内側に激しい感情を抱えているように感じました。
特に、他人の善意や「正しい言葉」がどれだけ暴力になり得るかというテーマに、胸が締めつけられました。
更紗も文も、自分の気持ちを言葉にするのがとても下手で、その不器用さが痛々しくもあり、でもどこか共感できました。
重めのテーマ
テーマが「世間からの偏見」「トラウマ」「生きづらさ」みたいなセンシティブな内容なので、“読みやすいけど感情的には重い”というタイプです。
セリフや地の文に派手さはありませんが、その分、登場人物の心の動きがじわじわ染みてくるように感じます。
感情を読み取ることが好きな人には、とても刺さると思います。
逆に、「スカッと爽快な展開を求めてる」「ハッピーエンドが絶対じゃないとイヤ」って人には、ちょっとしんどいかもしれない。
しかし、多くの方にとって心に残る一冊になるのではと思います。
以下、内容に触れた感想を記載しますので、開く際はその点ご了承ください。
感想(ネタバレ有り)
他の読者の感想
こちらをご覧ください。
※ネタバレ感想も含まれますので見る際はご注意ください。
まとめ
以上、凪良ゆうさんの「流浪の月」の読書感想でした。
社会に理解されない関係や、簡単には言語化できない痛み。それらを無理に説明せず、淡々と描いているからこそ、読後にいろんな感情が静かに残り続ける。そんな余韻のある一冊でした。
未読の方は是非手に取ってみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。