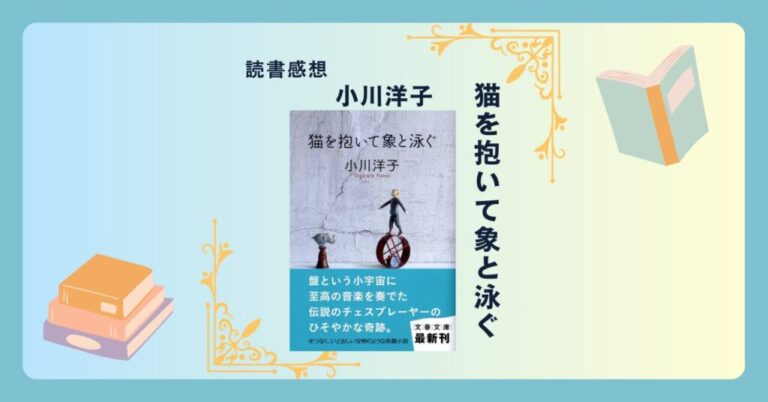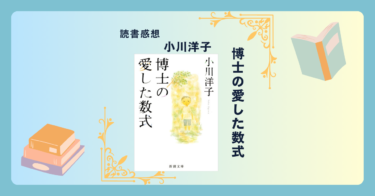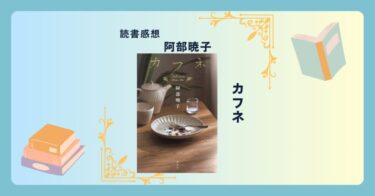読書感想です。今回は小川洋子さんの「猫を抱いて象と泳ぐ」です。
記事前半はネタバレは含みません。「続きを読む」を押さない限りネタバレ内容は見えませんので未読の方も安心してお読みください。
作品情報
- 作品名:猫を抱いて象と泳ぐ
- 作者 :小川洋子
- 出版社:文藝春秋(文春文庫)
- 頁数 :384P
こんな人におすすめ
- 静かで美しい物語が好き
- 孤独や成長について考えたい
- チェスや知的なゲームが好き
特徴グラフ
※私個人の見方・感想です。
あらすじ
『チェス盤の下に隠れている彼を、どうか見つけて下さい
伝説のチェスプレーヤー、リトル・アリョーヒンの、ひそやかな奇跡を描き尽した、切なく、愛おしい、宝物のような傑作長篇小説』
引用元:文藝春秋
感想
チェスが題材
チェスを題材にした物語です。
ただ、単なるゲームの話にとどまらず、人の成長や孤独、そして美しさについて考えさせられる内容です。
主人公の少年は、生まれつき唇にコンプレックスを持ち、人前に出ることを避けるようになります。
しかし、ある日出会った謎めいた男からチェスを学び、その才能を開花させていきます。
現実と幻想が溶け合う
主人公の彼は、通常のプレイヤーとは違い、自らの手ではなく「リトル・アリョーヒン」というからくり人形を使って駒を動かすようになります。
この設定がまず強烈です。
盤上の戦いは通常、プレイヤーの思考と指先が直結するものですが、彼は一歩引いた位置から対局を行います。
物語全体に漂うのは、繊細でどこか寂しげな雰囲気です。
現実と幻想が溶け合うような独特の美しさがあり、チェスの試合もただの勝負ではなく、一種の詩のように描かれます。
特に「盤下の詩人」と呼ばれる彼の指すチェスは、対戦相手の心理を読みながら、美しい棋譜を紡いでいきます。
この「美しい勝負」という概念は、勝ち負けだけにこだわる競技の世界とは異なり、芸術や哲学の領域に近いもののよう感じられます。
純文学寄り
直前に読んだ『博士の愛した数式』と比べると、物語のわかりやすさや感情の流れがつかみにくいかもしれません。
本作はストーリー性よりも、言葉の美しさや登場人物の内面の描写を重視しているように見え、純文学的な要素が強いように感じます。
「どう読めばいいのか」って迷うような、純文学ならではの感覚があるかもしれません。
淡々とした雰囲気
読みやすさやボリュームでいうと、そこまで長くはなありませんが、ストーリーに明確な山場があるわけではなく、静かに進んでいくので、一気読みというより少しずつ味わう感じの本かと思います。
淡々とした雰囲気を楽しめる人ならいいですが、テンポの良いストーリーを求めると、少し難しく感じるかもしれません。
以下、内容に触れた感想を記載しますので、開く際はその点ご了承ください。
感想(ネタバレ有り)
他の読者の感想
こちらをご覧ください。
※ネタバレ感想も含まれますので見る際はご注意ください。
まとめ
以上、小川洋子さんの「猫を抱いて象と泳ぐ」の読書感想でした。
独特の世界観と美しい文体が融合した作品です。チェスというテーマを通じて人間の内面や成長、孤独といった普遍的なテーマを描いています。じんわりと心に染みる物語が好きな人におすすめの一冊です。
未読の方は是非手に取ってみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。